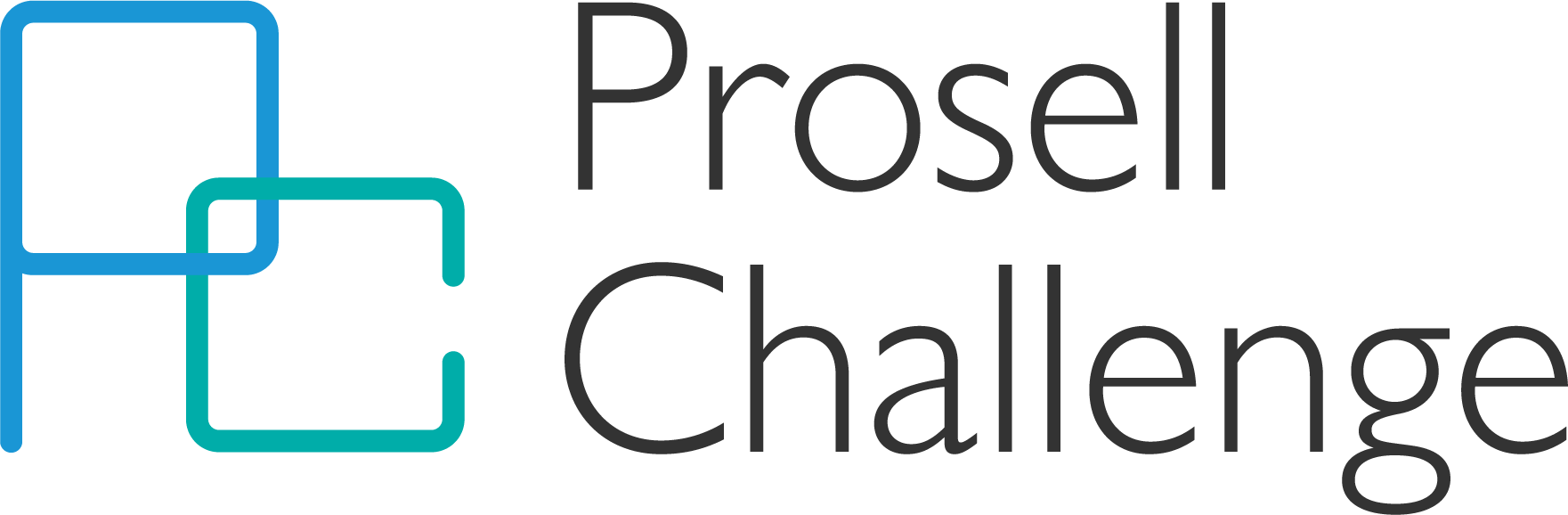上司からの厳しい叱責に、発達障がいが原因なのかと自分を責め、その言動が指導なのかパワハラなのか判断に迷っている方がいるかもしれません。その悩みは、正しい知識を身につけ、自分を守るための行動で、解決へと近づきます。
この記事では、パワハラの証拠の集め方、休職や退職の選択、「上司が発達障害かもしれない」と感じる方や、周囲ができるサポート方法まで、さまざまな立場の対策を解説します。
目次
パワハラに立ち向かうための具体的な準備と行動
上司からの不当な言動に苦しんでいる状況に、一人で立ち向かうのは簡単ではありません。ここでは、パワハラに立ち向かうための準備と行動を解説します。
有効な証拠の集め方
パワハラを第三者に認めてもらうためには、客観的な証拠が不可欠です。感情的な訴えだけでは指導の範囲内と反論される可能性があるため、具体的な証拠を継続的に記録し、保管しておく必要があります。
有効な証拠の1つ目は、暴言や人格否定発言の録音です。スマートフォンのアプリやICレコーダーを使い、パワハラ発言を記録します。相手の同意がない録音も、裁判などで証拠として認められる可能性あります。
2つ目は、メールやビジネスチャットの記録です。威圧的な文面や過大な業務要求が書かれたメッセージは、有力な証拠になり得ます。スクリーンショットを撮るなどして、会社の管理外の場所に保管しましょう。
3つ目は、日々の業務日誌です。いつ、どこで、誰に、何を、なぜ、どのように、を意識し、パワハラを受けた日時や場所、具体的な言動を詳細に記録しましょう。当時の心境や頭痛、不眠などの体調の変化も書いておくと、精神的な苦痛を証明する助けになります。些細なことでも記録を続けることで、パワハラが常態化している事実を示せます。
相談後の報復が怖い……不利益な扱いから身を守るには
「相談したことが上司に知られて、さらに酷い仕打ちを受けたらどうしよう」と、行動に移せない人もいるでしょう。しかし「労働施策総合推進法 第30条の2」により、企業はパワハラ防止措置を講じる義務があり、相談者に対する不利益な取り扱いも禁止されています。
「不利益な取り扱い」には、解雇だけでなく、降格、減給、望まない部署への配置転換などが含まれます。もし相談後に報復行為を受けたら、それは新たなハラスメント行為です。
自分を守るには、相談前から十分に証拠を集めることが肝心です。そして、社内のコンプライアンス窓口や人事部に相談する際には、相談した日時、担当者の名前、話した内容を詳細に記録しておきましょう。万が一、報復と思われる扱いを受けた場合、その事実も新たな証拠として記録し、外部機関へ訴える材料になります。会社の相談窓口が機能していないと感じた場合は、ためらわずに労働基準監督署や弁護士など、外部の専門家へ相談を切り替える判断も必要です。
障がいを打ち明ける?クローズからオープンにするメリット・デメリット
障がいの事実を職場に伝えるべきか(オープン就労)、伝えないままにすべきか(クローズ就労)は大きな悩みどころです。どちらにもメリットとデメリットがあり、自身の状況や職場の環境から慎重に判断しましょう。
オープン就労の最大のメリットは「合理的配慮」を求めやすくなることです。たとえば、口頭での指示が苦手なため文章での指示をお願いするなど、業務上の困難を軽減する配慮を求めやすくなります。パワハラが障がいへの無理解から起こっている場合、説明することで理解を得られ、不要な誤解を減らせるかもしれません。
一方、デメリットもあります。障がいへの偏見から、昇進や業務の割り当てで不利な扱いを受けたり、過剰に気を遣われ、かえって居心地が悪くなったりするリスクです。重要な仕事から外されるなど、成長の機会を失うかもしれないケースも考えられます。最終的には、会社の障がい者雇用への理解度や、信頼できる同僚がいるかなどを総合的に考えて判断しましょう。
休職・退職の選択肢

心身に不調を感じ始めたら、休職や退職も選択肢として考えましょう。
「もう少し頑張れる」と無理を重ねた結果、心と身体の限界を超えてしまうケースは多いです。そうなる前に、休職や退職を検討すべきサインを知っておくことが大切です。
心のサインは、朝起き上がれないほどの気分の落ち込み、理由のない涙、仕事への強い不安などが挙げられます。以前は楽しめていた趣味に興味がわかなくなるのも、心が疲弊している兆候です。
身体のサインも無視できません。寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚めるなどの不眠や、原因不明の頭痛や腹痛、食欲不振も危険信号です。客観的な行動の変化としては、遅刻や欠勤の増加、簡単な仕事でミスの連発などが挙げられます。これらが複数当てはまり、2週間以上続く場合は専門の医療機関を受診し、休職を含めた選択肢を真剣に検討するべきでしょう。
休職の手続き
休職する場合、一般的には医師の診断書を取得し、会社に提出して手続きを進めます。専門家である医師の判断を仰ぐことで、休職に入りやすくなります。
まず精神科や心療内科を受診し、職場の状況や心身の症状をできるだけ詳しく伝えましょう。医師が「休養が必要」と判断した場合、その旨が記載された診断書が発行されます。その診断書を会社の人事部や直属の上司に提出し、休職の意向を伝えましょう。
休職中の生活費は、傷病手当金の制度を活用します。加入している健康保険から給与の約3分の2が、最長で1年6ヶ月間支給される制度です。申請には、専用の申請書に医師と会社の証明を記入してもらう必要があります。
円満に退職するための手順と失業保険
休職しても状況が改善しない場合、退職が視野に入るでしょう。退職を決意したら、法的なルールや社会保険の手続きを理解したうえで計画的に進めていきます。
民法上は、退職の意思を伝えてから2週間で雇用契約は終了します。しかし、円満な退職のためには会社の就業規則に従うのが一般的です。直属の上司に退職の意向を伝えた後、退職届を提出します。
退職後の生活を支えるのが、失業保険です。自己都合での退職には通常約2ヶ月の給付制限がありますが、パワハラが原因の場合は「正当な理由のある自己都合退職」や「会社都合退職」として認められる可能性があります。この場合、給付制限なしで手当を受け取れるなど、受給条件が有利になります。認定には、ハローワークでの手続きの際にパワハラの証拠(医師の診断書、相談記録など)の提示が必要です。
【逆の立場】上司が発達障がいかもしれないと感じたら
これまでは部下が発達障がいの当事者であるケースを中心に解説してきましたが、「上司が発達障がいかもしれない」と感じ、その言動に苦しんでいる部下が悩んでいる場合もあります。上司の言動に悪気はなさそうに見えるものの、共感性が著しく欠けている場合、部下としてはどう対応してよいか分からなくなります。このような「逆の立場」の視点から、パワハラの問題と具体的な対処法を考えましょう。
発達障がいを持つ上司の言動の特徴とパワハラ該当性
部下の立場から上司を「発達障がい」だと診断することはできません。しかし、コミュニケーションに困難を感じる上司の言動が、発達障がいの特性として知られているものと似ているケースはあります。たとえば、場の空気を読んだり相手の感情を汲み取ったりすることが苦手で、悪気なく相手を傷つける発言をしてしまう、独自のルールに強くこだわり、少しでも違うやり方をすると過剰に叱責するなどです。
重要なのは、これらの言動が上司の特性に起因する可能性があったとしても、それによって部下が精神的な苦痛を受け、業務に支障が出ているならば、パワハラに該当し得る点です。パワハラの成立要件に、加害者側の意図は問われません。たとえ上司に悪気がなくても、客観的に見て業務の適切な範囲を超えた言動であれば、パワハラと判断されます。自分の苦痛を「上司の特性だから仕方ない」と我慢するのではなく、客観的な事実として捉えましょう。
我慢すべき?上手な対処法と付き合い方
上司に悪気がないかもしれないと思うと、強く反論できずに我慢してしまう人もいるでしょう。しかし、部下が一方的に我慢を続ける関係は健全ではありません。上司を変えることは難しくても、コミュニケーションの方法を工夫することで、状況を改善できる可能性もあります。
方法としては、具体的で明確な指示を仰ぐことが有効です。「〇〇ということでよろしいでしょうか」と具体的な言葉で確認し、認識のズレを防ぎます。報告や相談は、結論から先に、要点をまとめて簡潔に伝えることを心がけてみましょう。口頭でのやりとりに不安がある場合は、メールやチャットなど、記録に残る確認方法を徹底するのも一つの手です。自分の心を守るためには、上司の言動を人格攻撃と受け止めず、一歩引いて客観視することも大切です。一人で抱え込まず、信頼できる同僚や人事部などに「業務上のコミュニケーションで困っている」と相談してみるのもいいでしょう。
パワハラに悩む人へのサポート方法
身近な人がパワハラで苦しんでいると、家族や周りも辛いです。しかし、周囲の理解と適切なサポートは、本人が困難な状況を乗り越えるための大きな力になります。
本人の心を追い詰めない具体的な声かけとNGワード
パワハラにより、本人は自己肯定感が著しく低下し、「自分が悪いのではないか」と自分を責め続ける状態に陥りがちです。このときに必要なのは、批判や安易なアドバイスではなく、共感と肯定を基本とした声かけです。
まず、本人の話をじっくりと聞く「傾聴」の姿勢が必要です。「話してくれてありがとう。それは辛かったね」と、本人の苦しい気持ちを受け止めましょう。その上で、「何があってもあなたの味方だよ」と伝えることで、本人は孤独ではないと感じ、安心できます。
一方で、良かれと思ってかけた言葉が、かえって本人を追い詰めてしまうこともあります。「もっと頑張れば?」「気にしすぎだよ」といった言葉は、深刻な悩みを軽視されたと感じ、心を閉ざしてしまうかもしれません。「そんな会社、辞めちゃえばいいじゃない」という安易な解決策の提示も、本人が抱える生活やキャリアへの不安を無視した発言と受け取られかねません。本人の気持ちに寄り添い、安全な避難場所となる環境を整えることが大切です。
周囲ができること
精神的なサポートに加え、周囲は具体的な行動で本人を支えることもできます。心身ともに疲弊している本人が、一人で情報収集や手続きを進めるのは大きな負担です。
まずは、証拠集めの協力です。本人の代わりに話を聞いてメモを取ったり、ICレコーダーの準備を手伝ったりできます。パワハラと思われるメールのデータを、個人のパソコンに保存するように促すのも良いでしょう。
情報収集の代行も、大きな助けになります。本人の代わりに、労働基準監督署や発達障がい者支援センターなど、外部の相談窓口や利用方法を調べられます。また、休職や退職に関する社会保険制度を調べるのも、経済的な不安を和らげます。本人が希望すれば、病院や専門機関への相談への同行も心強いサポートです。
最も大切なのは、パワハラの原因を自分のせいだと責めず、一人で抱え込まないことです。パワハラに苦しんでいるなら、客観的な証拠を集め、しかるべき機関に相談することが、自分を守る第一歩になります。心身の限界を感じる前に、休職や退職など環境を変えるのも、決して逃げではありません。
もし現在の職場から離れ、自身の発達障がいの特性を理解し、強みとして活かせる新しい環境で働きたいなら、専門家の力を借りるのも有効です。
就労支援サービス「プロセルチャレンジ」は、発達障がいのある方の就職・転職を専門にサポートしています。特性に理解のある企業の紹介や、応募書類の添削、面接対策、入社後の定着支援まで、専門のキャリアアドバイザーが一人ひとりに寄り添い伴走します。まずは無料相談で、あなたの悩みやこれからのキャリアプランを話してみませんか。