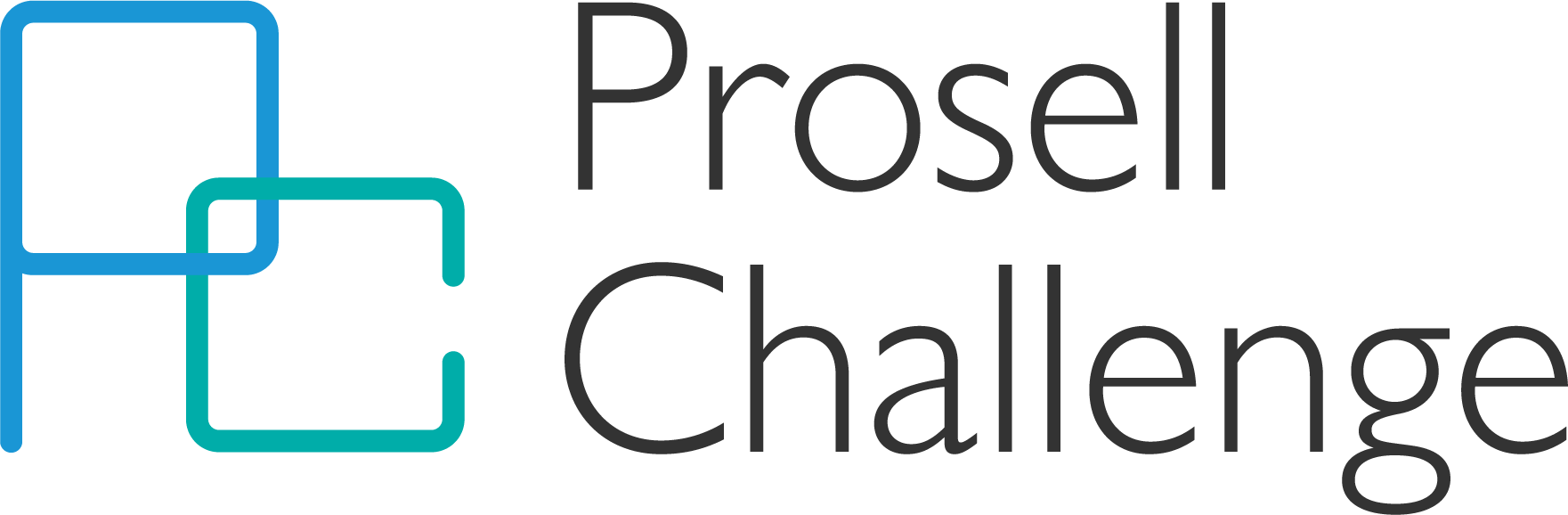面接で発達障がいのことを言うべきか言わないべきか、多くの方が悩むでしょう。障がいを隠した就職活動に問題はないのか、もし入社後にわかってしまったら、と不安もあるかもしれません。このような不安は、クローズ就労のメリット・デメリットを理解し、自分に合った働き方を見極める基準を持つことで整理できます。
この記事では、言わない選択肢の基本から、面接対策、入社後の働き方まで解説します。読み終える頃には、自分の状況に合った選択ができる知識が身につき、自信を持って一歩を踏み出せるでしょう。
目次
発達障がいを面接で「言わない」選択肢の基本と判断基準
発達障がいの特性を、就職活動の面接で言わない選択は、一度は考えたことがあるかもしれません。
ここでは、発達障がいを面接で言わないメリットとデメリット、入社後に障がいがわかった場合のリスクについて解説します。
クローズ就労で面接を受けるメリット
クローズ就労とは、自身の障がいを企業に開示せずに働くことです。最大のメリットは、障がいに対する先入観を持たれずに、個人の能力や人柄で評価されることです。障がい者手帳の有無にかかわらず、一般枠の求人に応募できるため、職種や業種の選択肢が大きく広がります。
健常者と同じ条件で採用されるため、入社後の昇給やキャリアアップの機会が平等に与えられる可能性も高まります。自分の能力を試したい、特定の分野で専門性を高めたいと考える人にとって、魅力的な選択肢の一つです。
クローズ就労で面接を受けるデメリット
クローズ就労には、障がい特性への配慮を得られないために、仕事で困難が生じる可能性があります。職場環境が自分の特性に合わない場合、本来持っている能力を発揮しにくく、ミスが増えたり業務効率が落ちたりするかもしれません。
たとえば、聴覚過敏の特性があるのに、電話が頻繁に鳴り響くオフィスで働くことになれば、業務に集中しにくくなります。マルチタスクが苦手な人が、複数の業務を同時にこなすよう求められると、混乱してしまうでしょう。
こうした状況が続くと、仕事ができない人と周りから誤解され、人間関係が悪化することも考えられます。結果として心身に不調をきたし、せっかく就職したのに、短い期間で離職せざるを得なくなる可能性は、あらかじめ理解しておかなければなりません。
入社後に障がいが発覚した場合、解雇される可能性は?
入社後に障がいが知られたとしても、ただちに解雇される可能性は低いです。日本の労働契約法では、企業が労働者を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、それが社会通念上相当であると認められなければなりません。
しかし、もし障がいの特性が原因で業務に支障が出ており、業務がこなせていない状況が続いた場合は、能力不足を理由に解雇を検討されるかもしれません。また、業務遂行に不可欠な資格や経験を虚偽申告していた場合、経歴詐称とみなされ、懲戒解雇の対象となる場合もあります。重要なのは、入社後に安定して業務を遂行できるかどうかです。
オープンとクローズ、あなたに合うのは?
オープン就労とクローズ就労のどちらが自分に合っているかは、個人の特性や求める働き方によって異なります。
1つ目は、必要な配慮のレベルです。自分なりの工夫やツールの活用で業務上の困難を乗り切れるのであれば、クローズ就労も選択肢に入ります。一方で、具体的な指示の出し方や静かな環境など、他者からの配慮がないと業務遂行が難しい場合は、オープン就労の方が安定して働きやすいでしょう。
2つ目は、精神的な負担の感じ方です。障がいを隠して働くことに不安を感じるなら、オープン就労の方が精神的に安定するかもしれません。逆に「障がい者のレッテルを貼られたくない」との気持ちが強いなら、クローズ就労を検討してみてもいいかもしれません。
3つ目は、キャリアプランです。幅広い選択肢から専門性を高めたい、昇進を目指したいと希望があるなら、求人数の多い一般枠(クローズ就労)が有利な場合があります。安定した長期勤務を最優先に考えるのであれば、職場定着のサポートが手厚いオープン就労も有力です。
「言わない」で面接を突破するための事前準備
発達障がいを面接で言わないと決めた場合、準備不足のまま面接に臨むと、意図せず特性が目立ってしまい、面接官に誤解を与えてしまう可能性があります。
自己分析で特性を強みに変え、企業研究でミスマッチを防ぐなど、具体的な方法を確認していきましょう。
特性を強みに変える自己分析
まずは自分の障がい特性を客観的に把握し、それを強みとして説明できるようにすることです。ここでは、障がいという言葉を使わずに、具体的な行動や能力で自分の得意なことと苦手なことを書き出してみましょう。
たとえば、こだわりが強い特性は、細部まで手を抜かずに、丁寧な仕事ができるという長所に言い換えられます。この能力は、品質管理や経理、校正など、正確さが求められる仕事で高く評価されるでしょう。
このように、自分の特性を弱みではなく、個性や能力として捉え直します。そして、その強みが応募する仕事でどのように活かせるのか、具体的なエピソードを交えて説明できるように準備しましょう。
苦手なことをポジティブに言い換える準備
面接では「あなたの短所は?」と質問されるのが一般的です。この質問に対して障がいに触れず、かつ前向きな印象を与える回答をあらかじめ準備しておくと安心です。ポイントは、苦手な事実だけを伝えるのではなく、それに対してどのように向き合い、改善しようと努力しているかを話すことです。
たとえば、マルチタスクが苦手な場合「一つの作業に集中して取り組むタイプです。そのため、複数の業務が重なった際には、優先順位を明確にして、一つずつ着実に終わらせるように工夫しています」と答えると、課題解決能力や誠実な人柄をアピールできます。
自分の苦手を自覚し、それに対する具体的な対策や改善意欲を示すことで、マイナスの印象が少なくなります。
自分の特性に合った職種を探す
自己分析で見えた強みを活かす職種を選ぶと、活躍できる可能性が高まります。発達障がいの人に「向いている」とされる仕事に固執するのではなく、あくまで自分の得意な作業や心地よいと感じる環境を軸に絞り込みましょう。
たとえば、一つのことに集中するのが得意で、ルールに沿った正確な作業を好むのであれば、経理、プログラマー、データ入力、品質管理といった職種が候補になります。
自分の強みがどの職種で活かせるかわからない場合は、ハローワークの専門相談員や転職エージェントのアドバイザーに相談し、客観的な意見をもらうのもいいでしょう。
発達障がいを言わずに就職した後の働き方

発達障がいの事実を面接で言わずに内定を獲得し、入社が決まったら、それはゴールではなく新しいスタートです。会社からの特別な配慮がない環境で安定して働き続けるためには、他の人以上に、自分自身で働きやすさを創り出す工夫が求められます。
入社後のミスを最小限にするための工夫
クローズで働く上で、自分の特性を理解し、業務上の困難を自力でカバーする仕組みを構築することは大切です。たとえば、口頭での指示を記憶するのが苦手な場合は、遠慮せずに「失礼ですが、後ほどチャットやメールでも内容を送っていただけますか?」とお願いしてみましょう。指示を文字で記録に残すことで、聞き漏らしや解釈のズレを防げます。タスクの抜け漏れが多い場合は、スマートフォンのリマインダー機能や、会社のPCで使えるタスク管理ツールを積極的に活用するのがおすすめです。
自分なりの「ミスを防ぐ仕組み」を確立し改善していくことが、周囲からの信頼を得ていく鍵です。
どうしても辛い時、最終手段としてのカミングアウト
あらゆる工夫を試みても状況が改善せず、心身ともに限界を感じたときには、上司や人事部に障がいをカミングアウトするのも、一つの選択肢として考えましょう。あくまで「最後の切り札」と位置づけ、安易に行うべきではありません。まずは自分でできる限りの努力をした上で、それでも業務に支障が出ているという客観的な事実にもとづいて相談することが大切です。
伝える際は、感情的にならず、具体的な事実を冷静に説明できるように準備します。「こういう特性があり」「この業務の、こういう点で困っていて」「たとえば、このようにしていただけると改善できます」のように、具体的な配慮案まで提案できると、相手も対応しやすくなります。医師の診断書があれば、話の説得力が増す場合もあるでしょう。
カミングアウトが必ずしも理解されるとは限りませんが、一人で抱え込んで心身を壊してしまう前に、状況を打開する手段として持っておくことが、自分を守ることにつながります。
合わないと感じた場合の対処法
入社後に「どうしてもこの職場は合わない」と感じた場合、無理をして働き続ける必要はありません。心身の健康を最優先に考え、異動や転職などの選択肢を視野に入れましょう。
まずは、合わないと感じる原因を具体的に分析しましょう。「特定の業務内容が合わない」「人間関係が難しい」など原因を切り分けると、次にとるべき行動が見えてきます。
原因が特定の業務や人間関係にあるなら、上司や人事部に相談し、部署異動を願い出る方法があります。柔軟に配置転換を検討してくれるかもしれません。一方で、会社そのものが自分に合わないと感じるなら、転職活動を始めるとよいでしょう。クローズ就労がうまくいかなかった経験は、決して無駄にはなりません。むしろ、次はオープン就労で自分に合った配慮のある環境を探すなど、より良い選択のための貴重な学びになります。
一人で悩まないで!「言わない」就活を相談できる支援機関
世の中には、障がいのある人の就職活動を専門的にサポートする支援機関が存在します。客観的なアドバイスをもらい、安心して就職活動を進めるため、積極的に活用しましょう。
就労移行支援事業所
障がいのある人が一般企業へ就職するために必要なスキル訓練から就職活動、就職後の職場定着を一貫してサポートする福祉サービスです。ビジネスマナーやPCスキル、コミュニケーション訓練など、働く上で土台となる能力を体系的に学べます。
特に、模擬面接を繰り返し行い、専門の支援員から客観的なフィードバックをもらえる点は大きな利点です。「言わない」と決めた場合の受け答えについても、より具体的で説得力のある話し方を一緒に考えてくれます。利用には市区町村が発行する障がい福祉サービス受給者証が必要になる場合が多いので、まずは近くの事業所を見学し、相談してみましょう。
ハローワーク
全国にある公的な就職支援機関であり、多くの事業所に障がいのある人を専門とする相談窓口が設置されています。発達障がいの特性を理解した専門の相談員が在籍しており、クローズ就労の希望も含め、親身に相談に乗ってくれます。
無料で利用できる職業訓練の案内や、面接対策セミナーなども定期的に実施しているため、情報収集の場として非常に有用です。クローズを主軸にしつつ、オープン求人の情報も並行して集める、といった柔軟な使い方も可能です。
転職エージェント
民間の職業紹介サービスであり、特にクローズでの転職を目指す場合、強力な味方となります。登録すると、専任のキャリアアドバイザーが担当につき、これまでの経歴や希望をヒアリングした上で、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれます。
転職エージェントを利用する最大のメリットの一つは、一般に公開されていない非公開求人を紹介してもらえる可能性があることです。また、アドバイザーは企業の内部情報(社風や残業の実態など)に詳しい場合が多く、ミスマッチの少ない企業選びの助けになります。
プロセルチャレンジも、その一つです。障がいのある方の就職・転職を専門にサポートしています。企業の紹介や、応募書類の添削、面接対策、入社後の定着支援まで、アドバイザーが一人ひとりに寄り添い伴走します。
まずは無料相談で、あなたの悩みやこれからのキャリアプランを話してみませんか。