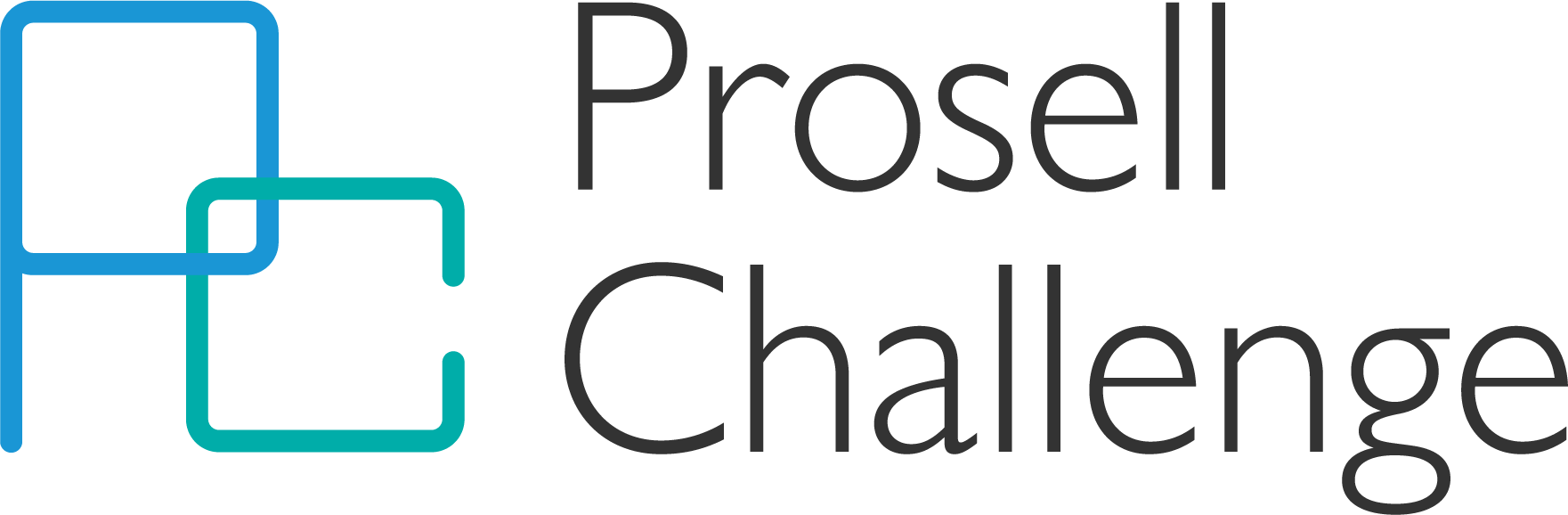配慮を求めたいけれど「どう伝えればいいのか」と悩んでいませんか。その悩みは配慮の求め方のコツと手順を知れば解決できます。
この記事では具体的な伝え方から、実際に交渉するステップまで解説します。不安なく会社と話し合い、自分らしく働ける環境を手に入れましょう。
目次
配慮の求め方・伝え方のポイント
障がい者の方が職場で能力を発揮するには、適切な配慮が欠かせません。しかし、いざ配慮を求めたくても「どう伝えればいいかわからない」「わがままだと思われないか」と悩んでしまうでしょう。ここで紹介する方法を参考にすれば、働きやすい環境作りに一歩近づけるはずです。
誰に・いつ・どう切り出す?相談の順番とタイミング
まず相談する相手は、原則として直属の上司です。なぜなら、日々の業務内容やチームの状況を最も理解しており、具体的な業務調整がしやすいためです。上司に相談しても解決が難しい場合は、人事部や社内の相談窓口、産業医など次の段階へ進むのが一般的な流れです。
相談するタイミングは、相手が話を聞く余裕のあるときにしましょう。
たとえば、1on1ミーティングが設定されていれば、その場で話すのが最適です。ない場合は、事前にアポイントを取りますが、始業直後や締切間近など、相手が忙しくしている時間帯は避けましょう。落ち着いた環境で話すことで、こちらの意図も正確に伝わりやすくなり、前向きな解決につながる可能性が高まります。
メールやチャットで依頼する際の書き方
口頭で伝えるのが難しい場合や、記録に残したい場合は、メールやチャットで相談しましょう。その際は要点を簡潔にまとめ、相手が理解しやすいように工夫します。
まず件名を見ただけで、業務に関する相談ということがわかるようにします。本文では、はじめに「業務の相談がしたく、ご連絡いたしました」のように、結論や目的を伝えます。その上で、現状の課題、障がい特性、具体的な配慮の依頼、配慮によって期待される効果を順に説明すると、論理的で説得力が増します。
能力不足やわがままだと思われない伝え方
配慮を求める際に多くの人が抱くのが、能力不足やわがままだと思われたくないという不安です。そうした誤解を避けるための伝え方のコツは、「できない」という否定的な表現ではなく、「こうすればできる」という前向きな姿勢を示すことです。
たとえば「疲れやすいので長時間の会議は無理」と伝えるのではなく「2時間以上の会議は集中力が途切れてしまうため、1時間ごとに短い休憩があると集中しやすい」のように伝えます。具体的な課題と解決策をセットで提案することで、単なる要求ではなく、業務改善のための前向きな提案として受け取られやすくなります。
また「この配慮をいただければ、より業務に集中でき、生産性を上げられます」のように、会社への貢献意欲を示すことも有効です。自分の都合だけを主張するのではなく、配慮を得ることで会社にとってもメリットがある、という視点を加えることで、わがままではなく必要な配慮と考えられやすくなります。
障がいをクローズのまま配慮を引き出す言い回し
障がいをクローズにして働いている場合でも、工夫次第で必要な配慮を引き出すことは可能です。その際の求め方のポイントは、障がい名を伏せたまま、具体的な症状や業務上の困りごととして伝えることです。診断名ではなく、誰もが経験しうる体調や特性の問題として説明することで、相手も状況を理解しやすくなります。
たとえば、パニック障がいの特性で満員電車が苦手な場合「人混みが苦手な体質のため、できれば通勤ラッシュを避け、時差出勤を許可してほしい」と相談できます。障がいそのものではなく、それによって生じる具体的な事象に焦点を当てて説明するのがコツです。ただし、障がいをクローズにしている場合、会社側に法律上の合理的配慮の提供義務は発生しません。あくまでも、お願いや相談程度になると理解しておきましょう。
特性や必要な配慮を整理する
配慮を求めるために、自分の状況を客観的に把握し、整理をしましょう。その際に役立つのが、厚生労働省などが提供している「支援シート」のようなフレームワークです。活用すると、自分の得意不得意、必要なサポートを言語化しやすいです。
活用方法は、シートの項目に沿って自分の特性を書き出してみます。「どのような環境で能力を発揮できるのか」のような得意な面と「どのような状況でミスが増えるのか」のような苦手な面を洗い出します。そしてそれに対し、どのような工夫やサポートがあれば業務がスムーズに進むかを考え、具体的な配慮案としてまとめましょう。
このプロセスを通じて、漠然としていた困りごとが明確になり、求める配慮が具体的になります。整理したシートは、上司や人事に説明する際の資料としても活用できます。自分の状況を客観的に見つめ直すツールとして、支援シートを試してみてください。
職場に求められる合理的配慮の具体例
他の合理的配慮の内容は、障がいの特性や業務内容、職場の環境によって千差万別です。代表的な例を知ることで、自分の状況に合った配慮を考えやすくなります。ここでは、職場に求められる合理的配慮の具体例を「障がい種別」「業務内容」「場面」の切り口から紹介します。これらの例は、全ての人に当てはまるわけではありません。自分の困りごとに近いケースを見つけ、会社に伝える際の参考にしてください。
障がい種別ごとの配慮
障がいの特性によって困りごとは異なります。そのため、求める配慮もさまざまです。
精神障がいのある方の場合、体調の波に合わせて働けるよう、短時間勤務や在宅勤務、通院のための休暇取得などが考えられます。ストレス管理のために、定期的な上司との面談や、相談しやすい担当者の配置も考えられます。
発達障がいのある方に対しては、指示の出し方を工夫する配慮がよく見られます。「あれをやっておいて」といった曖昧な指示ではなく「この資料を3部印刷して、ホチキスで留めてください」のように、具体的かつ一つずつ指示を出す方法です。感覚過敏がある場合は、パーテーションで仕切られた静かな席を用意するなど、環境面の調整も求められます。
身体障がいのある方への配慮は、物理的な障壁を取り除くものが中心です。視覚障がいがあれば音声読み上げソフトを導入したり、聴覚障がいがあれば筆談やチャットでコミュニケーションを取ったりします。知的障がいのある方には、作業手順を図やイラストで示したマニュアルを作成し、一つひとつの工程を丁寧に教えるといった配慮が有効です。
業務内容ごとの配慮
特性によって、特定の業務が苦手な場合があり、業務内容そのものの調整が必要です。
代表的な例が、電話応対の免除です。聴覚障がいや聴覚過敏、あるいは不安障がいなどで電話でのコミュニケーションが大きな負担になる場合に、その業務を免除してもらい、代わりにメールやチャットでの顧客対応する方法が取られます。また体力的な課題や定期的な通院が必要な方向けに、時短勤務やフレックスタイム制、時差出勤を認める配慮もあります。これにより本人の負担を軽減し、安定して長く働き続けられます。
その他にも、集中力が続きにくい方に対して、一度に多くの業務を任せず、業務量を調整したり、納期の長い業務を担当してもらったりする配慮があります。
場面ごとの配慮
必要な配慮は、入社後の日常業務だけに限りません。採用活動から日々の勤怠管理まで、さまざまな場面で配慮が求められます。たとえば採用面接の場面で、緊張でうまく話せない方のために、質問内容を事前に一部共有してもらったり、文字で質問を提示してもらったりする配慮が考えられます。また支援機関の担当者の同席を認めてもらうことも、安心して面接に臨むために有効です。
入社直後は、新しい環境に慣れるための配慮が求められます。研修のペースを調整したり、メンター役の先輩社員をつけたりすることで、スムーズな職場定着を試みます。
日々の勤怠に関する配慮もあります。定期通院が必要な場合、時間単位や半日単位で休暇が取得しやすい制度や、休暇取得の理由を詳細に聞かれないプライバシーへの配慮が求められます。
合理的配慮を求める4ステップ

配慮の求め方には、大きく分けて4つのステップがあります。一つひとつステップを踏み、働きやすい環境を作りましょう。
ステップ1:自己分析と準備
まずは、行動を起こす前の準備です。自分の状況を正確に把握し、言語化しましょう。具体的には「どのような業務の、どんな場面で困るのか」「その原因は何か」「どのような配慮があれば、その困りごとは解決するのか」を客観的に整理します。
この自己分析のプロセスは、専門家の視点を借りると精度が高まります。主治医やカウンセラー、就労移行支援事業所の支援員など、障がいや就労の知識を持つ第三者に相談してみましょう。本人が気づいていない課題や、より効果的な配慮案を提案してくれるかもしれません。
主治医の意見書や支援機関の推薦状など、客観的な書類も準備しましょう。第三者による専門的な見解は、会社に配慮の必要性を説明する際の助けとなり、説得力が高まります。感情的に訴えるのではなく、客観的な事実と具体的な解決策の準備が大切です。
ステップ2:会社との話し合い
次に、会社との話し合いの場を設けます。原則として、最初は直属の上司に相談しましょう。
当日はステップ1で準備したメモや資料を手元に置き、要点を整理しながら話します。もし一人で伝えるのが不安であれば、事前に会社の許可を得た上で、就労支援機関の担当者に同席してもらうのも手です。第三者が加わることで、客観的な視点から話し合いが進み、より建設的な結論に至りやすくなります。
ステップ3:配慮内容の決定と周囲への情報共有
具体的な配慮内容が決定したら、その内容を明確な形で記録に残します。口約束だけでは後に「言った、言わない」と認識違いが生じる場合があるからです。メールや面談記録、簡単な合意書などの文書にして、双方で確認・保管しましょう。
そして決定した配慮を行うために、関係する周囲への情報共有が必要になります。この情報共有は、上司から行ってもらうのが基本です。誰に、何を、どこまで伝えるかは本人のプライバシーに深く関わるため、必ず本人の意向を確認しながら慎重に進めます。
ステップ4:定期面談で配慮内容を見直す
合理的配慮は、一度決めたら終わりではありません。配慮内容が適切に機能しているか、定期的に見直す機会を設けることが不可欠です。以前は最適だった配慮が、いつの間にか現状に合わなくなっているケースは少なくありません。
具体的には、上司と1ヶ月に1回、あるいは3ヶ月に1回などの頻度で、定期的な面談の場を設けてもらいましょう。その面談で「現在の配慮はうまく機能しているか」「何か新しい困りごとは出てきていないか」などを話し合います。
見直しを通じて、配慮内容を柔軟に調整していくことが、長期的に安定して働き続けるための鍵となります。会社と継続的にコミュニケーションを取り、協力して働きやすい環境を作り上げる姿勢が、双方にとって良い結果をもたらします。配慮はゴールではなく、継続的なプロセスであると認識しましょう。
まとめ
職場への配慮の求め方について、具体的な伝え方のコツから会社と交渉するための4ステップまでを解説しました。自分らしく働き続けるために、配慮を求めることは正当な権利です。まずは自分の状況を整理し、伝え方をシミュレーションすることから始めてください。
自己分析や会社との対話に不安を感じる場合は、専門家のサポートを頼るのも有効です。プロセルチャレンジでは、専門家と共に自己理解を深め、自分らしい働き方を見つけるためのスキルが学べます。一人で抱え込まず、まずは無料相談で悩みを話してみませんか。一緒に最適な働き方を実現しましょう。