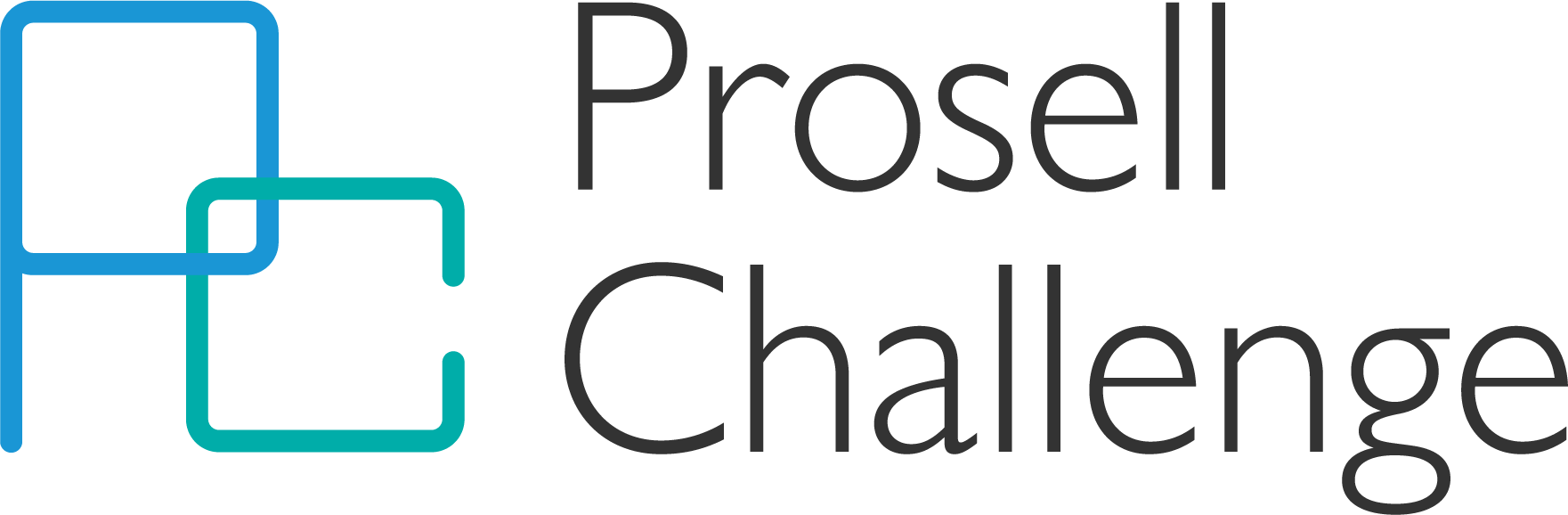精神障がい者の方が就職・転職活動をする際、面接での自己紹介を大きな壁に感じるかもしれません。面接官にマイナスの印象を与えないか、何を話せば評価されるのか分からず、不安になるのは自然なことです。
この記事では、精神障がい者雇用の面接における、自己紹介の作り方を解説します。障がいをポジティブに伝える方法や、面接への不安を和らげる準備方法も紹介します。自信を持って面接に臨むための参考にしてください。
精神障がい者雇用の面接|自己紹介のポイント
就職・転職活動をする際、面接の自己紹介は大きな関門の一つです。何をどこまで話せばよいのか、障がいについてどう伝えればいいのか、悩みは尽きないでしょう。
ここでは、精神障がい者雇用の面接における自己紹介のポイントを解説します。
自己紹介で伝えるべき4つの基本項目
面接の自己紹介では、いくつかの基本項目を盛り込むと、自分の人柄やスキルが伝わりやすくなります。企業側は、自己紹介を通じて応募者のコミュニケーション能力や経歴、仕事への意欲を把握しようとしています。今から紹介する4つの項目を意識して、自己紹介の内容を考えましょう。
名前と冒頭の挨拶
面接の第一声は、名前と挨拶から始めます。明るい表情と、はきはきとした声で「〇〇と申します。本日は面接の機会をいただき、ありがとうございます」と言いましょう。簡単な挨拶を丁寧に行うことで、基本的なマナーが身についている印象を与えられます。
また、感謝の言葉を添えることで、面接に真摯に向き合う姿勢も示せます。
これまでの職務経歴・実績やスキル
次に、今までの職務経歴や培ったスキルを説明します。過去の仕事内容を羅列するだけではなく、応募先の企業でどのように貢献できるかを意識して話しましょう。
たとえば、事務職への応募であれば「前職ではデータ入力や書類作成を担当し、正確かつ迅速なPCスキルを習得しました」のように、具体的なスキルと実績を結びつけて話します。軽作業の求人であれば「コツコツと一つの作業に集中することが得意です」といった特性をアピールするのもよいでしょう。
自分の経験から、応募職種に活かせそうなものを挙げ、企業が採用するメリットを感じられるように伝えましょう。
障がいについての簡単な説明
面接では、自身の障がいも説明する必要があります。障がい名を伝えるかは状況によりますが、少なくとも「どのような特性で、業務にどのような影響が出る可能性があるか」「そのために自分でどのような工夫や対策をしているか」を簡潔に伝えるのが基本です。
たとえば、「疲れがたまると集中力が途切れやすくなるため、1時間に一度5分ほどの休憩をいただくことで、集中力を維持しながら業務に取り組めます」といった具体的な説明です。企業側は必要な配慮を把握できると同時に、応募者が自身の障がいを客観的に理解し、対策を講じている安定した人材だという印象を持ちやすくなります。
志望動機と入社後の意欲
数ある企業の中から「なぜこの会社で働きたいのか」を明確に述べ、前向きな姿勢をアピールしましょう。企業理念や事業内容に共感した点、どのように貢献したいかなどを具体的に話すことで、熱意が伝わります。たとえば、「貴社の『一人ひとりに寄り添う』という理念に共感いたしました。私の強みである傾聴力を活かし、チームの一員として貢献したいです」のように述べます。最後にポジティブな意欲を示すことで、良い印象で自己紹介を終えられます。
自己紹介を成功させる3つのポイント
どんなに良い内容でも、伝え方一つで面接官に与える印象は大きく変わります。自信を持って、かつ的確に自分をアピールするために、話す内容だけでなく、話し方や時間配分にも気を配ってみましょう。
1〜2分程度に簡潔にまとめる
自己紹介の時間は、1~2分程度にまとめるのが一般的です。これより長くなると、面接官の集中力が途切れてしまい、本当に伝えたい要点がぼやけてしまいます。事前に話す内容を文章に書き出し、声に出して読んで時間を計りましょう。
伝えるべき要点を押さえる
限られた時間の中で効果的にアピールするためには、伝えるべき要点を押さえる必要があります。面接官が知りたいのは、人柄、スキル・経験、入社意欲、安定して働けるかです。これらを意識し、自分のアピールポイントを絞り込みましょう。
特に、応募する企業のホームページや求人情報を読み込み、どのような人材が求められているのか理解しましょう。その上で、企業のニーズと自分の強みが合致する部分を強調して話すと、より説得力のある自己紹介になります。自分本位なアピールに終始せず、相手が何を知りたいかを考えましょう。
ポジティブな第一印象を意識する
面接では話の内容と同じくらい、非言語的な要素が第一印象を左右します。緊張で顔がこわばってしまうかもしれませんが、少し口角を上げて笑顔を意識するだけで、親しみやすい雰囲気をつくれます。背筋を伸ばして良い姿勢を保ち、面接官の目を見て話すことも、自信や誠実さを示せます。声のトーンも、低すぎたり小さすぎたりすると自信がなさそうに見えるため、普段より少し明るく、はきはきと話すように心がけましょう。
こうしたポジティブな態度は、障がいの有無に関わらず、面接官に安心感や好印象を与えます。
障がいを強みに変えるアピール術
面接では、障がいを説明する場面があります。面接官は、応募者が自分の特性をどう理解し、どう仕事に活かそうとしているのかを見ています。障がいがあるからこそ発揮できる能力や、障がいと向き合う中で培われた姿勢を伝えることで、他の応募者にはない独自の価値を提示できるかもしれません。
ここでは、自己紹介で障がいをポジティブに伝えるための工夫を紹介します。
特性をポジティブに言い換える
自身の障がい特性をネガティブな側面から捉えず、ポジティブな側面に光を当てて言い換えましょう。自分の状態を客観的に理解しているアピールにもなります。たとえば「一つのことに集中しすぎてしまう」という特性は「一度始めた作業には深く集中し、高い精度で仕上げられる」と言い換えられます。
このように、短所に見える特性も、見方を変えれば長所になります。自分の特性をリストアップし、それがどのような場面でプラスに働くかを考えることで、自己PRの新たな切り口が見つかります。
面接官の「安定して働ける?」という不安を払拭するポイント
企業側が精神障がい者雇用で最も気にする点の一つが「安定して長く働けるか」という安定性です。これを払拭するには、自己紹介や質疑応答で、自身が安定就労のために行っている具体的な取り組みを伝えるといいでしょう。
たとえば「主治医の指示に従って服薬管理を徹底し、毎日決まった時間に就寝・起床することで生活リズムを整えています」と説明します。また、「ストレスを感じたときは、相談員や友人に話を聞いてもらったり、趣味の時間をつくったりして、一人で抱え込まないようにしています」といった具体的なストレス対処法を伝えるのも良いでしょう。
セルフケア方法を確立していると示すことで、面接官に安心感を与え、安定して業務に取り組める人材だと思われやすくなります。
自分の状態を正しく理解してもらい、長く働くための伝え方
長く働くには、入社後のミスマッチを防ぐことが何よりも肝心です。そのために、面接の場で自分を偽ったり、できないことを「できる」と言ったりしないようにしましょう。正直に、ありのままの状態を伝える勇気が求められます。
ネガティブな情報ばかりを並べる必要はありませんが、業務で必要な配慮は、きちんと伝えるべきです。たとえば、「一度に多くの指示を受けると混乱してしまうことがあるため、指示を一つずついただけると助かります」といった具体的な伝え方が有効です。
自分の状態を正しく理解してもらい、必要なサポートを事前に共有しておくことが、企業との信頼関係を築き、結果的に長く安定して働くための土台をつくります。
面接への不安や恐怖を和らげるための準備

「うまく話せるだろうか」「面接官にどう思われるか」と、不安や恐怖を感じるのは自然なことです。しかし、こうした不安は、事前準備をしっかり行うことで、ある程度和らげられます。
想定問答集を作成し、事前準備を徹底する
面接で聞かれそうな質問を予測し、それに対する回答をあらかじめ文章にまとめておく「想定問答集」の作成は、最も効果的な準備の一つです。特に自己紹介、障がいの説明、志望動機、長所と短所、退職理由は、ほぼ確実に聞かれる質問です。
これらの質問に対し、自分の言葉で回答を作成してみましょう。その過程で、自分の考えが整理され、アピールしたいポイントが明確になります。作成した回答は、ただ覚えるだけでなく、声に出して何度も読み上げて練習しましょう。スムーズに言葉が出るようになると自信がつき、本番での過度な緊張を防ぐ助けになります。
清潔感のある服装・身だしなみで臨む
服装や身だしなみは、第一印象に大きな影響を与えます。面接官は応募者の身だしなみから、常識や仕事に対する姿勢も判断しています。
基本的には、男女ともに清潔感のあるスーツを着用するのが無難です。事前にシワや汚れがないかを確認し、必要であればクリーニングに出しておきましょう。
髪型は顔がはっきりと見えるように整え、寝ぐせなどにも注意をしてください。爪が伸びすぎや汚れも、良い印象を与えません。こうした細部への気配りが、面接官に安心感を与えることに繋がります。家を出る前に、鏡で全身をチェックしましょう。
一人での面接対策に限界を感じたら
客観的なアドバイスが欲しくなったら、一人で抱え込まずに、公的な機関や民間の専門サービスを活用するのがおすすめです。障がい者雇用を専門とするスタッフから、求人紹介や面接練習など、きめ細やかなサポートを受けられます。専門家の視点からフィードバックをもらうことで、自分では気づかなかった強みや改善点が見つかるかもしれません。
ハローワーク
ハローワークには、障がいのある方の就職を専門にサポートする窓口があります。障がい者求人の紹介はもちろん、応募書類の添削や面接練習のサポートが無料で受けられます。職員は障がい者雇用の知識が豊富で、障がいの伝え方や必要な配慮の求め方など、具体的なアドバイスをもらえるのが大きなメリットです。地域の企業情報にも詳しいため、自分に合った職場を見つけやすいです。
就労移行支援事業所
障がい者の方が、一般企業へ就職するための知識やスキルを身につける訓練を行う、福祉サービスです。ビジネスマナーやPCスキル、コミュニケーション能力の向上などのプログラムに加え、個別のキャリアカウンセリングや面接対策も行っています。
実際の職場を想定した模擬面接を繰り返し行えるため、面接の雰囲気に慣れ、自信がつけられます。就職後の定着支援も行っており、入社後も相談できる心強い存在です。
利用には市区町村の障がい福祉窓口への申請が必要ですが、長期的に就職をサポートしてくれます。
転職エージェント
民間企業が運営する転職エージェントの中には、障がい者雇用を専門に扱うサービスもあります。専任アドバイザーが担当につき、求人紹介から面接の日程調整、給与などの条件交渉まで、転職活動全体をサポートしてくれます。
メリットは、企業側の採用担当者と密に連携しているため、企業の内部情報や求める人物像に詳しい点です。これを活かした模擬面接では、応募企業に合わせた、より実践的なアドバイスが期待できます。非公開求人を紹介してもらえるケースも多く、自分だけで探すよりも選択肢が広がります。多くのサービスは無料で登録できるため、情報収集の一環で活用するのもよいでしょう。
プロセルチャレンジでは、障がいのある方の就職・転職を専門にサポートしています。特性に理解のある企業の紹介や、応募書類の添削、面接対策、入社後の定着支援まで、アドバイザーが一人ひとりに寄り添い伴走します。
まずは無料相談で、あなたの悩みやこれからのキャリアプランを話してみませんか。